

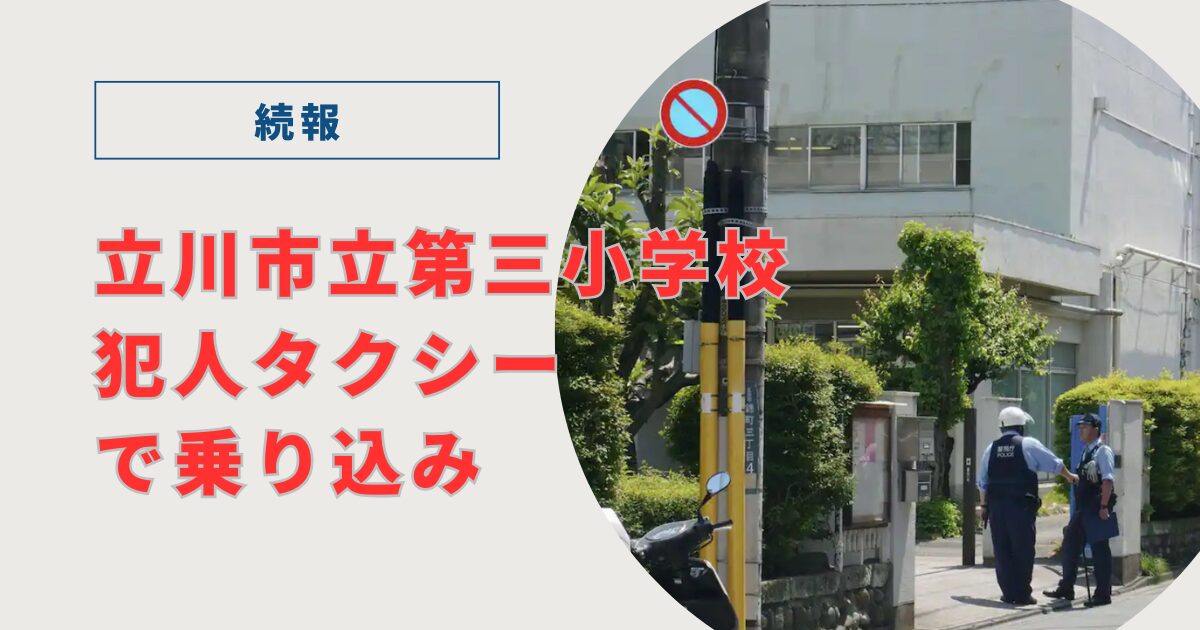
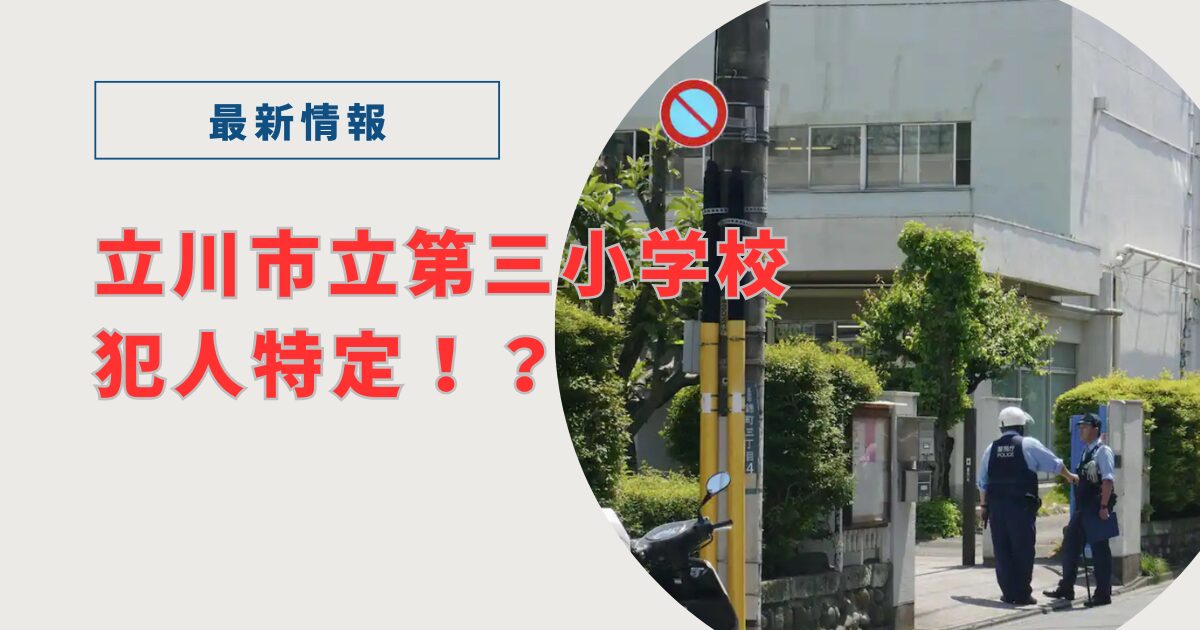
はじめに:あの日の朝、いつも通り送り出したはずなのに
2025年5月8日の朝、立川市立第三小学校に通う子どもたちの保護者は、いつものように「いってらっしゃい」と我が子を送り出したことでしょう。
給食の献立を確認したり、「体育がある日だから水筒忘れないでね」と声をかけたり。そんな日常が、午前11時前に突然崩れ去りました。
「学校で男2人が暴れて窓ガラスを割った」というニュース速報を目にした瞬間、どれほどの保護者が血の気が引く思いをしたでしょうか。
私も小学2年生の子を持つ母親として、このニュースを聞いたとき、真っ先に「もし自分の子どもだったら」と考えてしまいました。
今回は、同じ小学生保護者として、この事件について率直に感じたこと、そして私たち保護者が本当に知りたいこと、できることについて、一緒に考えていきたいと思います。
事件当日、保護者たちは何を感じていたのか
連絡が来た瞬間の心情
「先生がやられたから逃げるしかなかった」
これは事件を目撃した児童の言葉です。
小学2年生の口からこんな言葉が出るなんて、どれほど恐ろしい体験だったのでしょうか。
ある保護者は取材に対し、「ニュースの速報をみて駆けつけた。
まさか身近でこんなことが起きるなんて怖い。早く子どもに会いたい」と語っています。
この言葉に、多くの保護者の気持ちが凝縮されているのではないでしょうか。
学校からの連絡メールを受け取った瞬間の動揺、すぐに職場を早退したお母さん、仕事の会議中だったけれど飛び出していったお父さん。
みんな「生きた心地がしなかった」という思いを抱えながら、学校へと急いだのです。
迎えに行ったときの学校の様子
学校に到着すると、そこには警察車両や救急車が並び、規制線が張られた異様な光景が広がっていました。
「午前11時過ぎには緊急車両が小学校の道路近くに並んでいて、周囲には規制線が張られ、救急車が出入りするなど騒然とした雰囲気になっていた」とのことでした。
いつもの「お迎え」とは全く違う状況。「うちの子は無事なの?」「何が起きたの?」という不安と恐怖で胸がいっぱいになったことでしょう。
そして、我が子の顔を見た瞬間の安堵感。
「生きた心地がしなかった。子どもの顔を見られてほっとした」という保護者の言葉が、その時の心境を物語っています。
「保護者の知人」という事実に向き合う
衝撃的な事実:犯人は保護者の知人だった
事件の詳細が明らかになるにつれ、私たちを最も驚かせたのは、侵入した2人が「児童の母親の友人」だったという事実でした。
「保護者が午前中に担任と面談をしていた。
面談後に学校を出た保護者が、関係者とおぼしき男性2名を学校に連れて戻ってきた」という経緯が判明し、衝撃が走りました。
「まさか保護者が関わっているなんて」 「子どものトラブルで、こんなことになるなんて」
保護者同士の会話でも、この話題で持ちきりでした。
誰もが「自分は絶対にそんなことはしない」と思いつつも、「でも、どうしてそこまで追い詰められたのだろう」という疑問も抱いていました。
子どものトラブルと親の感情
報道によれば、事件の背景には「いじめ対応を巡るトラブル」があったとされています。
正直に言えば、子どもがいじめに遭っていると知ったとき、親として冷静でいられる自信がある人はどれくらいいるでしょうか?
「うちの子が誰かにいじめられている」 「学校が適切に対応してくれない」 「話を聞いてもらえない」
そんな状況に直面したとき、親として何ができるでしょうか。
多くの保護者が、「気持ちはわかる。
でも、やり方が間違っている」と感じたのではないでしょうか。
「自分だったら」という自問自答
この事件を受けて、多くの保護者が自問自答しました。
- もし自分の子どもがいじめに遭っていたら?
- 学校との話し合いが上手くいかなかったら?
- 誰に相談すればいいのか?
- どこまでが適切な対応なのか?
私自身、この事件を知ってから、改めて「子どものトラブル時の対応」について家族で話し合いました。
感情的になることは人間として当然ですが、その感情をどうコントロールし、適切な行動に移すかが重要だと感じています。
子どもたちの「その後」が心配
事件を目撃した子どもたちの様子
「(教室に)入ってきて先生がやられた時、怖かった。鼻血とか血のあとがあった」という児童の証言は、読んでいてとても辛くなりました。
また、「友達は(容疑者を)見たと言っていた。メガネをかけてて、瓶を下に落として、それに血がついていたと」という証言も。
子どもたちは、安全であるはずの教室で、想像を絶する光景を目にしてしまったのです。
「ほとんどみんな泣いていた」という保護者の証言からも、子どもたちがどれほどショックを受けたかがわかります。
「もう学校に行きたくない」と言われたら
事件後、多くの保護者が心配したのは「子どもが学校に行きたがらなくなるのではないか」ということでした。
実際、事件の翌日、お腹が痛いと言って登校を渋る子、「先生は大丈夫?」と何度も聞いてくる子など、様々な反応が見られたそうです。
私の知り合いの子どもは、その夜「もう死んじゃうのかな」とつぶやいたといいます。
たった7〜8歳の子どもが、死の恐怖を感じるような体験をしてしまったのです。
心のケアはどうすればいい?
立川市教育委員会は「本日の状況を目撃した児童も多く、心理的なケアをするために、スクールカウンセラーや市の心理士を派遣して、今後丁寧な対応をはかる」と発表しました。
これは心強い対応です。
でも、家庭でもできることがあるはずです。
保護者仲間と話し合った結果、以下のようなことに気をつけることにしました:
- いつも以上にスキンシップを大切に
- ハグの時間を増やす
- 一緒にお風呂に入る
- 添い寝をする
- 子どもの話をじっくり聞く
- 「怖かったね」と共感する
- 無理に話させない
- 子どものペースに合わせる
- 日常のリズムを大切に
- いつもの習い事は続ける
- 好きな食べ物を用意する
- 楽しいことも計画する
- 学校との連携を密に
- 子どもの様子を先生に伝える
- カウンセリングの活用
- 必要なサポートを遠慮なく求める
学校の安全対策、本当はどうなっているの?
「誰でも入れる」は本当だった?
保護者の間で最も話題になったのは、学校のセキュリティ問題でした。
ある保護者は「誰でも入れるしセキュリティが甘かったのか」と疑問を呈しています。
また、「誰でも入れると、前から心配していた」という声も上がっていました。
立川市教育委員会は「通常の学校運営においては、不特定多数の人物が学校外から入るところは拒むような形での運営をしている」と説明していますが、「実際、施錠等がしてあたのかどうかというところについては確認の方が取れていない」とも述べています。
保護者として知りたいこと
私たち保護者が本当に知りたいのは、以下のようなことです:
- 誰が学校に入れるのか?
- 保護者はいつでも入れるの?
- 身分証明書の提示は必要?
- 事前の連絡は必須?
- 緊急時の対応は?
- 不審者侵入時のマニュアルはあるの?
- 子どもたちの避難訓練は?
- 保護者への連絡方法は?
- 防犯設備の現状は?
- 防犯カメラはついているの?
- 警備員はいるの?
- 緊急通報システムは?
- 今後の改善策は?
- いつまでに何が変わるの?
- 保護者の意見は反映されるの?
- 定期的な見直しはあるの?
他の学校ではどうなの?
この事件を受けて、他の小学校に通う保護者たちとも情報交換をしました。驚いたのは、学校によってセキュリティレベルがかなり違うということです。
- A小学校:正門に警備員が常駐、保護者も名札必須
- B小学校:オートロックシステム導入済み
- C小学校:防犯カメラのみ、日中は門が開いている
「うちの学校は大丈夫なの?」と不安になった保護者も多いはずです。
保護者同士で話し合ったこと
「うちの学校でも起こりうる」という危機感
事件後、保護者のグループLINEは情報交換の場となりました。そこで共有されたのは、「これは立川第三小学校だけの問題ではない」という認識でした。
「うちの学校でも校門が開けっ放しの時がある」 「参観日は誰でも入れる状態」 「名札をつけていない人を見かけたことがある」
こうした不安の声が次々と上がりました。でも同時に、「だからこそ、私たち保護者ができることがあるはずだ」という前向きな意見も出てきました。
保護者ができる具体的なアクション
話し合いの結果、以下のような行動を起こすことにしました:
- PTAを通じた要望書の提出
- セキュリティ強化の具体案
- 定期的な防犯訓練の実施要請
- 保護者向け安全講習会の開催
- 見守り活動の強化
- 登下校時のパトロール参加者を増やす
- 校門での声かけ運動
- 不審者情報の共有システム構築
- 子どもたちへの安全教育
- 「いかのおすし」の徹底
- 緊急時の対応方法の確認
- 助けを求める練習
- 学校との定期的な意見交換
- 月1回の安全対策会議
- アンケートの実施
- 改善状況の確認
感情的にならない対話の重要性
この事件から学んだ最も大切なことの一つは、「感情的にならずに対話することの重要性」でした。子どものことになると、どうしても感情が先走りがちです。でも、それが今回のような結果を招いてしまうこともあるのです。
保護者同士で話し合い、以下のルールを決めました:
- まずは深呼吸:カッとなったら、一旦立ち止まる
- 複数で相談:一人で抱え込まず、他の保護者にも相談
- 段階的な対応:担任→学年主任→管理職→教育委員会
- 記録を残す:面談の内容は必ずメモを取る
- 冷静な第三者の同席:必要に応じて、中立的な立場の人に同席してもらう
子どもを守るために、今すぐできること
家族で話し合おう
この事件をきっかけに、多くの家庭で「もしも」の話をしたそうです。我が家でも、以下のようなことを話し合いました:
- 学校で怖いことがあったら
- すぐに大人に助けを求める
- 大きな声を出す
- 安全な場所に逃げる
- 知らない人が学校にいたら
- 先生にすぐ報告する
- その人に近づかない
- 友達にも教える
- お母さん、お父さんに言いにくいことがあったら
- 他の信頼できる大人に相談してもいい
- スクールカウンセラーもいる
- 電話相談もできる
学校との連携を強化しよう
「生徒を守った先生たちをしっかりケアしてほしい」という声も上がっています。先生方も被害者なのです。この機会に、改めて学校との信頼関係を築き直すことが大切だと感じました。
具体的には:
- 感謝の気持ちを伝える
- 子どもを守ってくれた先生方にお礼を
- 日頃の指導への感謝も忘れずに
- 建設的な提案をする
- 批判だけでなく、改善案も一緒に
- 実現可能な提案を心がける
- 協力できることは協力する
- 見守り活動への参加
- 学校行事のお手伝い
- 情報提供への協力
地域全体で子どもを守る
「子どもは地域の宝」という言葉があります。学校だけでなく、地域全体で子どもたちを守る体制を作ることが大切です。
- 近所の人との連携
- 顔見知りを増やす
- 子どもの様子を気にかけてもらう
- 異変があったら連絡し合う
- 子ども110番の家の活用
- 場所を子どもに教える
- 実際に訪問してみる
- お礼を言いに行く
- 地域イベントへの参加
- 子どもも大人も顔見知りに
- コミュニティの結束を強める
- 孤立を防ぐ
まとめ:子どもの笑顔を守るために
立川市立第三小学校での事件は、私たち保護者に大きな衝撃と不安を与えました。
でも同時に、「子どもを守るために何ができるか」を真剣に考えるきっかけにもなりました。
「児童の安全を全力で守って下さった教職員に感謝致します」という立川市教育委員会の言葉通り、先生方は文字通り身を挺して子どもたちを守ってくれました。
その勇気に感謝しつつ、今度は私たち保護者が、学校と地域と協力して、子どもたちの安全を守る番だと思います。
子どもの笑顔は、私たち大人の宝物です。
その笑顔を守るために、感情的にならず、でも真剣に、できることから始めていきましょう。
「行ってらっしゃい」と送り出した子どもが、「ただいま」と元気に帰ってくる。
そんな当たり前の日常を、これからも大切にしていきたいと思います。
あなたの学校では、どんな安全対策がとられていますか?良いアイデアがあれば、ぜひコメント欄でシェアしてください。
みんなで知恵を出し合い、子どもたちの安全を守っていきましょう。
学校の安全対策について不安を感じたら、一人で悩まず、他の保護者や学校に相談しましょう。
みんなで協力すれば、きっと良い解決策が見つかるはずです。
